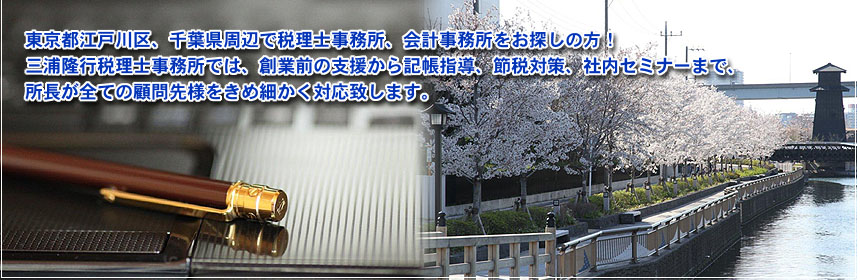日常の事務手続きを行うだけでは、
企業の財政状態や経営成績は明らかにはならないため、
決算という手続きが必要になります。
一会計期間の末日を決算日と言います。
個人事業主では決算日が12月31日と決められています。
株式会社の場合は特に決まりがありませんが、大半は3月31日です。
決算の手続きは決算日当日に行うのではなく、
個人事業者は、翌年の2月16日~3月15日に申告します。
一会計期間の収益や追加の発生額を整理し修正をします。
1.有価証券の評価替え-株の上昇や下昇の評価額
2.現金過不足の整理-分からない場合は雑益や雑損に振り替える必要があります
3.消耗品の整理-使ったものは明確にしておく、また残数は幾らであるか
4.売上原価の計算-儲けが幾らか調べます
5.固定資産の減価償却-土地や建物、車など価値の減少を見ます
6.貸倒引当金の設定-可能性として、収金出来なるものを見積もります
7.費用・収益の見越し・繰り延べ―次期分費用が含まれているときは、当期から費用を除く必要があります
会社の目標は、事業を行って利益を上げていくこと
事業をよりスピーディに大きくするための支出をすることで、
それが経費となり、結果として税金が節約できます。
事業投資が節税対策に有効です。
来期購入予定の備品を購入するとか、
広告費用を増加させるとか、採用に係る費用を前倒しでかけるとか、
事業をスピーディでかつ大きくするために当期中に行える有効な事業投資がないか検討します。
もし有効な投資を今期中に行うことができれば、
投資を行うことで結果として節税することが出来るのです。
【参考サイト】
決算直前の節税対策
http://hgand.co.jp/